【2024年版】インバウンドマーケティングとは
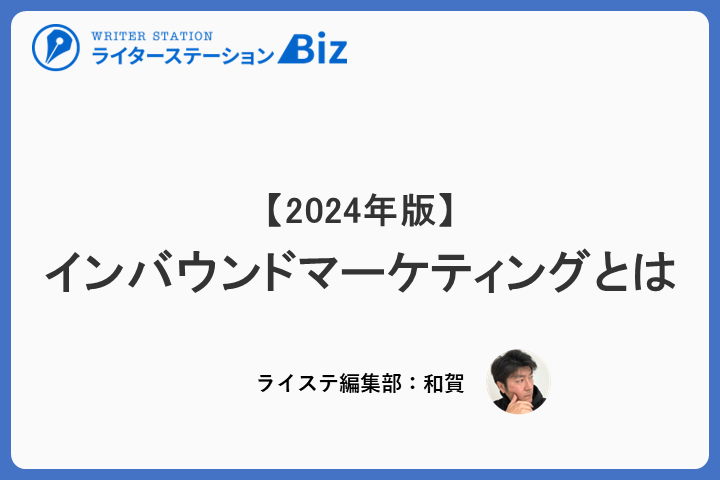
Table of Contents
インバウンドマーケティングとは
インバウンドマーケティングとは、価値のあるコンテンツを提供し顧客の関心を集めるマーケティング手法です。顧客が自らコンテンツを見つけ、企業や商品に魅力を感じてもらうことにより、成約に結びつけます。顧客に製品やサービスを一方的に奨めるのではなく、顧客の課題を解決できる点を自然にアピールするのがポイントです。
インバウンドマーケティングの例としては、以下のコンテンツが挙げられます。
- SEO
- オウンドメディア
- コンテンツマーケティング(ホワイトペーパー、メルマガなど)
- SNSマーケティング
- 動画コンテンツ
- イベント・セミナー
なお、インバウンドと聞くと訪日外国人旅行を思い浮かべる方もいらっしゃいますが、インバウンドマーケティングは訪日外国人をターゲットとしていません。
インバウンドマーケティングの重要性
近年は顧客の購買行動が変化しているため、インバウンドマーケティングの重要性がより一層高まっています。2000年代以降はインターネットが急速に発展し、パソコンやスマートフォンで素早く情報を入手できるようになりました。
以前は商品を購入する際、テレビや折込チラシなどで情報を入手し、各店舗を訪れて商品を比較・検討していたものです。今ではGoogleで商品を検索し、比較サイトなどを材料にして商品を決めるケースも少なくありません。
顧客が実店舗に加えてオンラインから購入のアクションを起こすようになったため、従来の営業活動だけで顧客を惹き付けるのが難しくなりました。そのため、宣伝を広告に固執するよりも、顧客がいつでも情報を得られるコンテンツを展開するインバウンドマーケティングの方が重要となっているのです。
アウトバウンドマーケティングとの違い
アウトバウンドマーケティングとは、テレビやラジオの広告、ダイレクトメールなどを利用し、積極的に顧客へ情報を届ける手法のこと。顧客の意思に関わらず企業が主体となって売り込みをかけるため、「プッシュ型」とも呼ばれています。
インバウンドマーケティングはアウトバウンドマーケティングの対義語で、顧客に直接情報を売り込まずに購買行動を促す手法のことです。顧客が意思を持ってコンテンツを選ぶため、「プル型」とも呼称されます。
重要なのは自社の商品やサービスを利用する人の目線で考える
インバウンドマーケティングのポイントは、顧客の目線に立つことです。コンテンツを作成する際は、顧客が「いつ」「どこで」「どんなとき」に商品やサービスへ行き着くのかを意識する必要があります。自社の商品やサービスの利用が想定される顧客を選定し、どのような課題やニーズを持っているかを調査しましょう。
ターゲット顧客に対する理解を深め、最後まで読んでもらえるコンテンツを作成することは、インバウンドマーケティングにおいて欠かせません。
近年はSNSなどの発信手段が豊富にあるため、企業と顧客の距離は近づいています。そのため、オンライン上で積極的に顧客とコミュニケーションを行い、良好な関係を構築するのも有効です。顧客がSNSで商品に対する不満を投稿しているのを確認し、返品対応や謝罪などを行う企業もあります。顧客の切実な声を誠実に受け入れれば、企業と顧客の信頼関係を継続できるでしょう。
インバウンドマーケティングのメリット・デメリット
インバウンドマーケティングのメリットは以下の通りです。
- コストを削減できる
インバウンドマーケティングは従来の広告と比べ、運用にかかる費用を抑えられます。外部に広告を出す際は広告費がかかりますが、自社でコンテンツの運用を完結させれば広告費が発生しません。インターネット広告で集客する場合も、テレビや新聞などの広告よりコストを低減できます。 - 顧客から信頼を得られる
インバウンドマーケティングは強制的に商品を販売せず、顧客が欲しいと思ったコンテンツを購入する仕組みのため、顧客からの信頼を得やすいのが特徴です。自ら情報を検索して価値ある情報が手に入れば、顧客は企業に対して信頼を抱くでしょう。 - 長期的な収益が期待できる
インバウンドマーケティングによりコンテンツを作成すれば、インターネットに存在する資産となります。定期的に顧客がコンテンツを購入すれば、長きに渡り収益を得られるでしょう。時間をかけて人気コンテンツに成長させれば、企業の名声も高まります。
一方、インバウンドマーケティングには以下のデメリットもあるため、注意が必要です。
- 収益までに時間がかかる
インバウンドマーケティングにより作成したコンテンツは、アクセスされるまで時間がかかります。コンテンツが検索上位に表示されるまでは中々収益が得られないため、短期間での成果を求めるのは向いていません。 - コンテンツ作成後も改善を繰り返す必要がある
インバウンドマーケティングによりコンテンツを作成した後も、アクセス解析やコンテンツの編集など様々な作業が必要となります。コンテンツの改善には専門知識が求められ、社内の人員が不足している場合はコンサルタントの費用がかかるかもしれません。
インバウンドマーケティングのターゲットを設定しよう
バイヤーペルソナの定義と作成方法
バイヤーペルソナとは企業にとって理想的な顧客を具体的に表現したもので、日本では単にペルソナと呼ばれるのが一般的です。インバウンドマーケティングを効果的かつ効率的に進めるには、バイヤーペルソナの設定が欠かせません。バイヤーペルソナは架空の人物でも良く、年齢・性別・職業・家族構成などの詳細な情報を設定し、人物のイメージがはっきり浮かぶように設定する必要があります。
バイヤーペルソナを作成する際は、以下の順に行うことがポイントです。
- 顧客情報を収集・分析する
まずは顧客リストを用意し、合計購入金額・平均購入金額・居住地域などの細かな情報を集めましょう。様々な切り口から情報を分析することにより、理想的な顧客像がはっきりします。実在する顧客だけでなく潜在的な顧客についても調べるのも、コンテンツの方向性を定める上で重要です。 - 社内のメンバーに聞き込みする
社内で顧客のことをよく理解している営業・サポート担当者に、バイヤーペルソナを作成する目的や考えを話し、理想的な顧客とは何かについて質問しましょう。担当者から詳しい情報を聞き出せれば、顧客が求めているものが見えてきます。 - 顧客にインタビューする
実際の顧客にもインタビューを行い、様々な意見をヒアリングしましょう。営業・サポート担当を経由するか直接顧客に依頼をし、インタビュー日時の調整を行います。質問事項をあらかじめ顧客に伝えておけば、インタビューをスムーズに進行させることが可能です。インタビューだけで情報が足りない場合は、アンケートなど別の手段も検討します。 - バイヤーペルソナを作成する
これまでの調査結果を基にして、バイヤーペルソナを作成しましょう。テンプレートを用意すれば、バイヤーペルソナを作りやすくなります。 - 社内でバイヤーペルソナを共有する
作成したバイヤーペルソナは、社内の営業・サポート担当者と情報を共有しましょう。営業・サポート担当者とバイヤーペルソナに対する考えを合わせ、優良顧客の獲得に前向きであることをアピールするのがポイントです。営業・サポート担当者とマーケティング担当者が密接になり、営業・マーケティング活動の効率がアップします。 - 適宜バイヤーペルソナを見直す
マーケティング活動を進めていくと、バイヤーペルソナが想定と異なる場合もあるでしょう。そのため、都度社内で話し合いを行い、バイヤーペルソナを修正・改善することが求められます。
バイヤージャーニーの理解
インバウンドマーケティングの成功率を高めるには、バイヤージャーニーの理解を深めるのも重要です。バイヤージャーニーとは、バイヤーペルソナ(顧客)が製品・サービスを発見し、比較・検討して購入に至る一連のプロセスを指します。
バイヤージャーニーは、「認識」「検討」「決定」と3つのステージに分けられるのが特徴です。
- 認識ステージ
認識ステージとは、顧客が自ら抱える課題やニーズに気付く段階のことです。顧客は課題やニーズに対する理解を深めるために情報収集などを行います。 - 検討ステージ
検討ステージとは、顧客が課題やニーズを明確にした上で解決方法を検討する段階のことです。顧客は課題を解決できる可能性がある商品・サービスに興味を持ち、様々な選択肢を比較・検討します。 - 決定ステージ
決定ステージとは、顧客が解決策を決定する段階のことです。顧客は認識・検討のステージを経て商品・サービスを絞り込み、課題がクリアできるものを購入します。バイヤージャーニーはBtoB(企業間取引)のケースが多いため、意思決定者が複数存在することを考慮しなければなりません。
バイヤージャーニーの各ステージで何が求められ、どのような対策をすべきか理解すれば、より効果的なマーケティング戦略を展開できます。自社の商品・サービスがそれぞれのステージに対応しているかを意識してコンテンツを作成しましょう。
インバウンドマーケティングの手法を選ぼう
SEO
SEOはSearch Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略で、ウェブサイトを検索エンジンの上位に表示し、見込み顧客に発見されやすくするための手法です。検索エンジンはユーザーの検索ワードから疑問や悩みなどを推測し、課題の解決に繋がると判断したサイトを優先的に表示します。
例として、Google検索で「iPhone 新型」と検索する場合を考えましょう。検索エンジンは新しいiPhoneのスペック情報などをユーザーが求めていると判断し、関連性や信頼性の高いサイトを1ページ目に持ってきます。
インバウンドマーケティングでより多くの顧客を集めるためには、SEO対策を入念に行うことが重要です。サイトの内容がどれだけ魅力的であっても、SEO対策が十分でなければ検索結果の上位に表示されず、人々の目に留まりません。
常に人々が検索しているキーワードを選定して記事のタイトルや見出しに入れれば、サイトが検索結果の上位に表示され続けます。長期にわたってアクセス数が高水準で推移すれば、収益の安定が見込めるでしょう。内部リンクなどを挿入してユーザーが使いやすいサイトにすることも、検索エンジンに評価してもらうためには欠かせません。
オウンドメディア
オウンドメディア(Owned Media)とは企業が自社で保有しているメディアのことで、商品・サービスのマーケティングを目的とする媒体の一種です。自社で展開するブログ記事などを指すのが一般的で、採用情報や自社のブランディングなどを目的とする企業公式サイトと区別されます。
オウンドメディアから読者にとって有益な情報を発信して信頼を勝ち取れば、最終的に商品やサービスを購入してもらうことが可能です。オウンドメディアで成果を出すには時間がかかりますが、認知され続ければ継続的な利益をもたらします。従来の広告と比べるとコストが安価に抑えられる傾向があり、費用対効果が高いのも利点です。
オウンドメディアを成功に導くためには、以下のポイントを意識する必要があります。
- 読者のニーズに合った質の高いコンテンツを作成する
コンテンツの質を高めるには、独自性・専門性のある情報を盛り込み、他のオウンドメディアとの差別化を図ることが重要です。コンテンツを作成する際はバイヤーペルソナやバイヤージャーニーを設定し、読者のニーズに合致するかを分析しましょう。 - 社内の体制を整備する
オウンドメディアの運営には多くの工程があるため、社内の体制を整備することも求められます。業務の片手間で取り組むのではなく、企画・執筆・編集などオウンドメディア専門の人員を配置しましょう。 - 定期的にコンテンツを見直す
定期的に内容をアップデートすることも、オウンドメディアの運営をしていく上で欠かせません。解析ツールによるアクセス内容の分析などを行い、オウンドメディアの改善に繋げましょう。
ホワイトペーパー
ホワイトペーパーとは、見込み顧客に向けて企業が作成する資料のことです。導入事例・調査レポート・入門ガイドなどの情報をまとめ、Web上でダウンロードできる状態にして提供します。
ホワイトペーパーは、氏名・企業名・メールアドレスなどの情報を入力してダウンロードする仕組みです。ホワイトペーパーを入手する見込み顧客は、個人情報を提供してでも中身を知りたいと考えるため、購買意欲が高い傾向にあります。インバウンドマーケティングでホワイトペーパーを上手く活用できれば、成約率がアップするでしょう。
ホワイトペーパーを展開する上で重要となるポイントは以下の通りです。
- 情報は必要な分だけにする
ホワイトペーパーの情報が長すぎると、読者は途中で離脱してしまうかもしれません。最後まで集中して読んでもらえるように、必要な情報をシンプルにまとめましょう。 - 理解しやすい構成にする
ホワイトペーパーの内容を効果的に伝えるためには、構成を工夫することが重要です。問題提起や解決策の提示をして読者の関心を高め、ページの最後にある問い合わせ先にアクションさせる、という流れを作りましょう。 - 魅力のあるデザインにする
ホワイトペーパーの内容をより良くするには、魅力のあるデザインに仕上げることも欠かせません。レイアウトの工夫や図表の挿入などを行い、視覚的に訴えかけるデザインにしましょう。
SNS
X(Twitter)・Instagram・FacebookなどのSNSも、インバウンドマーケティングにおいて重要な役割を果たします。SNSは多くの利用者が気軽に閲覧できる媒体のため、オウンドメディアやホワイトペーパーなどへの誘導が期待できるのです。
SNSは無料で始められるため、コストを抑えて企業の宣伝を行えます。SNSの投稿が多くのユーザーにシェアされ、好意的な意見をもらえれば、企業の認知度もアップするでしょう。
SNSの運用をする場合は、以下のポイントを抑えることが重要です。
- バランスの良い投稿をする
商品・サービスの機能面を重視しすぎると固い印象を与え、親しみやすさに重きを置くと購入に中々結び付きません。機能面と親しみやすさをバランス良く発信できるよう、投稿の内容を工夫しましょう。 - それぞれのSNSに合わせた運用をする
SNSは多くの種類があり、それぞれのユーザー層は異なっています。Instagramであれば印象に残る写真を投稿し、Facebookであれば企業理念を発信するなど、運用するSNSに応じて投稿内容を最適化しましょう。 - ハッシュタグを活用する
ハッシュタグを適切に入れて投稿すれば、ユーザーは検索結果から投稿を見つけやすくなります。ハッシュタグを選定する場合は、ターゲットとするユーザーの視点に立つのがコツです。
メルマガ
メルマガ(メールマガジン)を配信するメールマーケティングも、インバウンドマーケティングに分類されます。メルマガは登録している顧客・見込み顧客に送信されるため、購買行動に繋がりやすいのが特徴。SNSの普及により、コミュニケーション手段としてメールはあまり使われなくなりましたが、ECサイトなどのマーケティング手段としては今も有効です。
メールマーケティングを成功に導くためには、以下のポイントを理解することが重要となります。
- 受け手が満足するメルマガを作成する
どのような層に配信するかを明確にし、受け手がメリットを得られるメルマガを作成しましょう。メールの件名や本文を簡潔かつメリットがすぐ分かるものにすれば、購読率がアップします。 - 定期的に配信する
メルマガの受け手が商品・サービスを理解し、優良顧客になるためには、定期的に配信することが重要です。メルマガを送りすぎると受け手が迷惑と感じる場合もあるため、受け手の状況を把握し適切な頻度で送信しましょう。 - 送信したメルマガを分析する
メルマガは単に送信するのがゴールではなく、送信後にメールの開封率・メールリンクへの遷移率・配信解除率などを可視化することも欠かせません。様々な数値を分析し、メルマガの改善策を検討しましょう。
動画コンテンツ
動画コンテンツを制作してYouTubeなどで公開する動画マーケティングも、インバウンドマーケティングで使われる手法です。動画コンテンツは視覚・聴覚に情報を伝えるため、視聴者に強い印象を与えることができます。また、動画は短時間で多くの情報を盛り込めるため、効率的な情報の発信が可能です。
動画コンテンツを作る際は、以下のポイントを重視しましょう。
- 動画のクオリティを高める
動画コンテンツはスマートフォンだけでなく、テレビなどの大画面で視聴される場合もあります。動画の画質・音声をできるだけ高品質なものにすれば、より多くの視聴者を獲得できるでしょう。 - 動画のサムネイルを魅力的なものにする
動画コンテンツを検索して最初に見られるのが、動画の内容を画像にしたサムネイルです。動画の内容が伝わりやすく独自性があるサムネイルを作成し、動画のクリック率を上げましょう。 - 動画で適切なキーワードを使用する
YouTubeに動画をアップロードした場合、コンテンツ内のキーワードはテキスト化され、検索結果に表示するために使われます。動画が検索されやすいよう、キーワードを効果的に使用しましょう。
イベント・セミナー
イベント・セミナーの開催も、インバウンドマーケティングにおける効果的な手法です。近年はオンラインで開催されるイベント・セミナーが多く、家や会社にいながら気軽に企業の声を聞けるようになりました。イベント・セミナーは顧客に直接商品・サービスの情報を伝えるため、顧客の信頼を築きやすいのがメリットです。
イベント・セミナーを実りあるものにするため、以下のポイントを押さえましょう。
- 適切に集客する
イベント・セミナーの集客手段はSNS・メールなど様々です。ターゲットに応じて集客手段を使い分け、参加率を高めましょう。開催日をリマインドすることも、参加人数の増加に繋がります。 - 開催中に企業と参加者のコミュニケーションの場を設ける
イベント・セミナーではただ情報を伝えるだけでなく、質問時間を設けるなどして参加者との間でコミュニケーションを図りましょう。参加者の反応などを見ることで、柔軟に内容を調節できます。 - 終了後のフォローアップを行う
イベント・セミナーが終了した後も、参加者のフォローアップが欠かせません。特典が付いたアンケートの用意や、素早いお礼メールの送信などを行い、参加者との関係を維持しましょう。
インバウンドマーケティングのPDCAを回そう
インバウンドマーケティングの成果を測定するための指標
インバウンドマーケティングを行う際は、KPI(Key Performance Indicator)と呼ばれる指標の活用が重要です。KPIを日本語に訳すと「重要業績評価指標」となり、現在の目標がどの程度達成できているかを評価します。インバウンドマーケティングで設定すべき主なKPIは以下の通りです。
- 営業売上
営業売上は、インバウンドマーケティングにおいて最も重要なKPIとなります。売上が目標に届いているかを確認し、目標未満であればマーケティング戦略を見直さなければなりません。 - ROI(投資収益率)
ROI(Return On Investment)は、かけた費用に対してどのくらいの収益を得られたのかを評価する指標です。ROIが高い数値であれば、費用対効果が高いと言えます。ROIは利益金額(売上から費用を差し引いた金額)を費用で割るだけで算出可能です。 - CAC(顧客獲得コスト)
CAC(Customer Acquisition Cost)とは、1人の顧客を獲得する際にかかった総コストのこと。費用対効果の高い顧客獲得ルートを把握でき、マーケティング活動の効率化に繋がるのがメリットです。CACは顧客獲得費用を新規顧客数で割って算出します。 - LTV(顧客生涯価値)
LTV(Life Time Value)は、顧客が一生を通じてどのくらいの利益をもたらすかを評価する指標です。LTVを算出すると長期的な利益を計測でき、予算の振り分けなどの判断材料となります。LTVの代表的な計算方法は、「顧客の平均購入単価×平均購入回数」です。 - CVR(コンバージョン率)
CVR(Conversion Rate)とは、Webサイトを訪問したユーザーが商品・サービスの購入などに至る確率のこと。ユーザーにとって魅力的なサイトにするため、CVRを元に改善策を検討しましょう。
データ分析と改善のサイクル
インバウンドマーケティングでは、KPIを用いてPDCAサイクルを回すことが重要です。PDCAはPlan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)を取ったもので、目標管理の手法として幅広く使われています。Planから順にPDCAサイクルを実行し、データ分析・課題改善を繰り返すことは、インバウンドマーケティングの成功への鍵です。
以下でPDCAサイクルの各ステップで何を行うべきかを説明します。
- Plan
まず、インバウンドマーケティングで何を達成したいかを明確にし、目標に基づいたKPIを選定しましょう。KPIの基となる指標は可能な限り多く洗い出し、明確に達成すべきものを優先してKPIとします。 - Do
Planのステップで設定したKPIを達成するため、SEO対策やコンテンツマーケティングなどの業務に取り組みましょう。Doで得られたデータは次のステップで利用するため、事細かに記録します。 - Check
Doのステップをある程度実行した後は、KPIの達成率を評価しましょう。過去の事例と現在の実績を比較するなどして、収集したデータを客観的に分析します。 - Action
Checkステップで明確になった課題に対し、改善策を立案するのが最後のActionステップです。改善策を実行した後は再びPDCAを回し、更なる改善に取り組みます。
インバウンドマーケティングを効率化しよう
マーケティングオートメーションの概要
マーケティングオートメーション(MA)とは、企業のマーケティング担当者が手作業で行っている多くの業務を自動化(オートメーション)し、効率的にマーケティングを進めるためのシステムを指します。
以前はリード(見込み顧客)が商品やサービスを知る手段は営業・セミナーなどに限られていたため、業務にかかる工数は少なく済みました。近年はインターネットが普及し、リードが容易に商品やサービスの情報を収集できるように。より多くのリードを獲得できると同時に作業工数が増加傾向にあるため、MAツールが求められているのです。
MAツールは、リードを獲得する「リードジェネレーション」、リードの購入意欲を育てる「リードナーチャリング」、リードを絞り込む「リードクオリフィケーション」に対応。リードの行動に基づいてパーソナライズされたメールを自動で送信し、リードの商品・サービスへの関心度合いを数値化するなどして、リードの獲得をサポートします。
MAツールであればリードを一括で管理でき、受注確率が高いリードへの効果的なアプローチが可能です。インバウンドマーケティングとMAツールを組み合わせることにより、企業と顧客のコミュニケーションが加速します。
ワークフローの作成と活用
インバウンドマーケティング活動の生産性を上げるには、MAツールに備わっているワークフロー作成機能の活用が欠かせません。ワークフローとは、ある目標を達成するために行う業務の流れを表す言葉です。MAツールを用いてワークフローの自動化を進めることにより、マーケティングにかかる工数を減らし、より多くの顧客へ適切なアプローチを行えます。
代表的なMAツールであるHubSpotでワークフローを作成する手順は以下の通りです。
- オブジェクトの設定
まずはワークフローによって達成したいオブジェクト(目的)を設定します。一から細かく情報を入力するだけでなく、テンプレートを利用して簡単にワークフローを開始することも可能です。 - トリガーの設定
オブジェクトの設定が完了したら、トリガーを設定します。トリガーとは、ワークフローでアクションを発生させるきっかけとなるイベントのことです。トリガーの設定により、ユーザーの行動ごとに異なるアクションを引き起こせます。 - アクションの設定
次の手順は、ワークフローで起こすアクションの設定です。メール・SMSの送信など、様々な選択肢から実行したいアクションを選択しましょう。アクションの実行日時などを適切に設定すれば、ワークフローを効果的に運用することができます。
インバウンドマーケティングの今後
インバウンドマーケティングの要点のまとめ
今回の記事では、インバウンドマーケティングについて解説を行いました。
インバウンドマーケティングとは、顧客にとって有益なコンテンツを作成し、商品・サービスに興味を持ってもらうマーケティング手法です。近年はインターネットが普及し、顧客がオンライン上で購買行動を起こすのが一般的になったため、インバウンドマーケティングが注目されるようになりました。
インバウンドマーケティングは成果が出るまで時間がかかるものの、従来のアウトバウンドマーケティングよりコストを抑えられ、顧客からの信頼やコンテンツの資産化が期待できます。
インバウンドマーケティングの手法は、SEO対策・オウンドメディア・SNSなど様々です。いずれのコンテンツも、読者が課題を解決できるよう魅力的な内容にする必要があります。
インバウンドマーケティングにおいて重要なのは、顧客の視点に立ってマーケティング活動を進めることです。バイヤーペルソナやバイヤージャーニーを作成し、顧客が何を求めているかを十分に把握する必要があります。
営業売上やCVR(コンバージョン率)といったKPIの設定も、インバウンドマーケティングを行う上で欠かせません。KPIを確認すれば、目標の進捗がどのくらいかを把握できます。KPIを用いてPDCAサイクルを繰り返し実行し、客観的な視点でデータを分析して課題を解決していきましょう。
インバウンドマーケティングの効率をアップするには、MAツールの導入が効果的です。MAツールを活用すればマーケティング業務を自動化し、少ない工数で大きな成果を上げることができます。MAツールでワークフロー作成機能を使用し、顧客に応じて様々なアクションを自動で実行させましょう。
今後のマーケティングのトレンドと展望
ChatGPTなどの生成AIが急速に発展していることも、近年インバウンドマーケティングの需要が高まっている要因です。生成AIの台頭は、コンテンツ作成の分野において大きな影響を及ぼしています。
生成AIは質問に素早く回答できるため、文章を短時間で作成することが可能です。プロンプト(質問文)をより具体的なものにすれば、生成AIが返す文章のクオリティは大幅に向上します。結果として文章の修正が少なく済み、短い時間でコンテンツを公開可能な状態にできるのです。
以前であれば、SEOを意識してコンテンツの作成を行うのはとても手間のかかる作業でした。生成AIはSEOも考慮して文章を生成してくれるため、キーワードの選定にかかる時間を大幅に軽減できます。
未来のマーケティングにおけるトレンドは、生成AIとマーケティングのさらなる統合です。生成AIは今後も進化を続け、顧客が求めているものを詳細に分析し、より訴求力が高いコンテンツを作成できるようになるでしょう。将来のマーケティング戦略で優位に立つためには、生成AIの進化を常に追い、より効果的かつ独自性のあるアプローチを模索することが重要です。
Zenken株式会社が運営する「ライターステーションBiz」は、インバウンドマーケティングをより効果的に行えるようHubSpotの導入をサポートしています。HubSpotにはAI機能が備わり、高品質なSNSやブログなどの文章を自動で生成することが可能です。最適なプロンプトを提案する機能もあり、複雑な指示文章を覚えなくとも情報を得られます。
より良いコンテンツを作成したいと思っている方は、ライターステーションBizまでご相談ください。
この記事を書いた人

- 1,200名以上登録されてるライタープラットフォーム:ライターステーション責任者。2024年より「記事作成代行サービス」や「Hubspot導入支援」、「インタラクティブ動画」など、コンテンツマーケティングに関する支援を開始。
最新の投稿
 コンテンツマーケティング2024-06-14BtoBマーケティングのためのウェビナー活用法
コンテンツマーケティング2024-06-14BtoBマーケティングのためのウェビナー活用法 コンテンツマーケティング2024-06-13コンテンツマーケティングで見込める効果とは?
コンテンツマーケティング2024-06-13コンテンツマーケティングで見込める効果とは? 記事作成2024-06-11記事作成代行サービスを利用するメリットとポイントをご紹介!
記事作成2024-06-11記事作成代行サービスを利用するメリットとポイントをご紹介! 記事作成2024-06-06【2024年版】セールスライティング大全【独自ノウハウも有】
記事作成2024-06-06【2024年版】セールスライティング大全【独自ノウハウも有】



