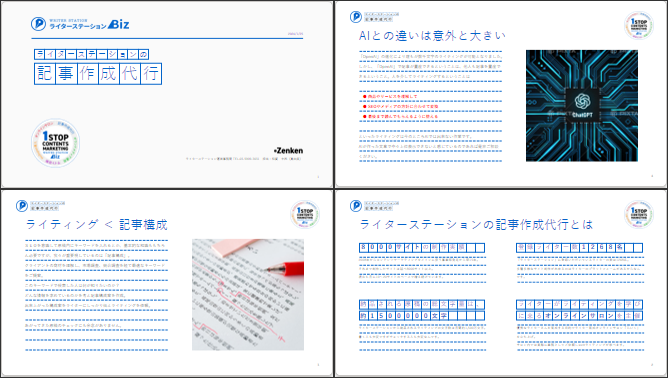医療広告ガイドラインにおける「口コミ」について

2018年6月に厚生労働省により改定・適用された「医療広告ガイドライン」。
これまで医療広告といえば、テレビCMやチラシ、新聞や雑誌の広告欄などが対象で、人の命にかか わるものとして医療法により厳しく規制されてきました。
しかし、今回改定された「医療広告ガイドライン」では、これまで対象ではなかっ た「ホームページなどのwebサイト」も新たに規制の対象とし、表現方法や掲載内容に関して制 限されるようになったのです。
Table of Contents
なぜ見直しがされたのか?
そもそも、医療広告ガイドラインの目的は、「患者に誤認を与えず、正確で有益な情報を 提供すること」。
今回の改定の背景には、美容クリニック関連の公式サイトで特に不適切なサイトが多くあったことから、その規制強化がありました。
人の健康や人生に関わる情報は、正確な情報を慎重に扱うべきだとされています。そこで医療を提供する側が発信する情報に規制をもたせ、誤認などのトラブルが起きないようにしているのです。
医療広告ガイドラインの見直しによって広告の対象となったホームページなどのwebサイト。ここでは、広告における「口コミ掲載」について解説します。
ホームページは広告。口コミ掲載はNG!
省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当 該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味するものであるが、こうした体験談 については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、 医療に関する広告としては認められないものであること。
これは、患者の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない 。引用:医療広告ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf
改定医療広告ガイドラインによると、広告とみなされるものについては「治療内容や効果についての口コミ掲載」は認められません。
口コミ掲載はなぜNG?
クリニックなどの医療機関の口コミというと、その施設の雰囲気や対応、治療やサービス の内容、その効果や感想などが記載されています。
これらの口コミの需要は高いもの。同じ悩 みを持つ人たち、その医療機関を受診しようと考えている人たちにとって、実際にそこで 治療を受けた人の声は知りたい情報でしょう。
しかし、ひとりの患者の感想や治療結果は、そのほかの人に必ずしもあてはまるわけでは ありません。
また、残念ながら、口コミの中には、誇大に脚色されていたり(いわゆる「 盛られて」いたり)、その医療機関に有利になるような情報だけが強調されているものも 少なくありません。
このような口コミを見た人が、自分にも当てはまると信じて医療サービスを受けた結果、 思わぬ損害を被ることもあるほか、ときには健康や命にかかわることもあるのです。
こうした背景を踏まえ、医療広告において治療内容や効果に関する口コミの掲載は禁止になりました。
[writing_agency]
口コミNGとなる「広告とみなされるサイト」の範囲とは
今回の医療広告ガイドライン改定では、「ホームページなどのwebサイト」も広告とみなされるようになりました。しかし、web上のページすべてが広告に該当するかといえば、そうではありません。
①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称 が特定可能であること(特定性)引用:医療広告ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf
広告とみなすには、上記の「誘引性」と「特定性」に有無があるかどうかで判断されます 。
なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期 待して誘引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を 推薦している内容であったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして 取り扱うこと。ただし、当該病 院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は 効果に関する体験談については広告に該当すること(その上で省令第 1 条の 9 第 1 号の規 定に基づき禁止されること)。
また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合 も該当するものであること。引用:医療広告ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf
医療機関側が患者の来院を促す目的があるwebページなどには、「誘引性」があります 。(医療機関の公式サイト、医療機関が制作・運営する情報サイトなど)
一方、新聞記事などで新聞社がある医療機関をとりあげて紹介したとしても、医療機関か らの働きかけがなければ「誘引性」はありません。(不特定多数の医療機関の情報を扱う サイト、口コミサイト、自分のブログやSNSなど)
ただし、医療機関が新聞社に掲載を依頼していたり、広告費を支払ったりする場合は「誘引性あり」とみなされるということです。
また、治療方法を紹介する目的のwebサイトであっても、医療機関の名称や電話番号など 特定できる情報が含まれている場合は広告とみなされます。
誘引性の有無がポイント
患者等が自ら掲載する体験談、手記等自らや家族等からの伝聞により、実際の体験に基づ いて、例えば、A病院を推薦する手記を個人Xが作成し、出版物やしおり等により公表し た場合や口頭で評判を広める場合には、一見すると本指針第2の1に掲げた①及び②の要 件を満たすが、この場合には、個人XがA病院を推薦したにすぎず、①の「誘引性」の要 件を満たさないため広告とは見なさない。
ただし、A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている又はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものとして扱うことが適当であ る。 また、個人XがA病院の経営に関与する者の家族等である場合にも、病院の利益のためと 認められる場 合には、①の「誘引性」を有するものとして、扱うものであること。引用:医療広告ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf
たとえば、患者が自ら自分のブログやSNSなどに口コミとして体験談を掲載することは、 医療機関による働きかけがないため「誘引性なし」。
しかし、その口コミや体験談が医療機関から依頼されたものである、金銭などの謝礼を受けている場合には医療機関からの働きかけがあるため「誘引性あり」となります。
基本的な考えとして、有償無性に関わらず“医療機関からの働きかけがある口コミ掲載は「 誘引性あり」でNG”と覚えておきましょう。
医療機関が働きかけていなくても責任を負うケース
しかし、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿を依 頼していない場合であっても、例えば、当該ウェブサイトの運営者が、体験談の内容を改 編したり、否定的な体験談を削除したり(当該体験談が名誉毀損等の不法行為に当たる場 合を除く)、又は肯定的な体験談を優先的に上部に表示するなど体験談を医療機関の有利 に編集している場合、それが医療機関からの依頼によって行われたものであるときには誘 引性が生じます。
また、仮に医療機関の依頼により行われたものではないとしても、事後的に医療機関がそのように編集されたウェブサイトの運営費を負担する場合には、当該編集された体験談に 誘引性が生じると考えられます。引用:医療広告ガイドラインに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000371826.pdf
医療機関を検索できるwebサイトなどにおいて、第三者であるwebサイト運営者が口コミ を掲載した場合はどうでしょう。
たとえ医療機関が「肯定的な口コミ掲載をしてほしい」と依頼していなくても、サイト運 営者が口コミ掲載の違反をすることは考えられます。
- サイト運営者が 肯定的な口コミだけを掲載する
- 肯定的な口コミが目立つようにする
- 口コミ内容をアレンジする
- 否定的な口コミを削除する
などの行為をした場合、サイト運営者は広告規制の対象として罰せられます。そして、医療機関がサイト運営者に口コミに関する依頼や指示をしていなくても、「違反内容の あるサイト制作・運営の費用を事後的に払う」ことで、同様に罰せられるので注意が必要です。
違反のあるサイトの運営費を支払ったことで、「サイト運営者が勝手にやった」とは言えないということです。また、口コミランキングサイトなども医療広告ガイドラインでは禁止されています。 口コミの数や評価などからランキングをし、特定の医療機関を強調することはできません 。
限定解除要件を満たせば、口コミは掲載可能か?
医療広告ガイドラインでは、規制された表現について「限定解除要件」を満たせば記載可能な内容があります。
しかし、口コミ掲載については触れられていません。 つまり、解釈としては「口コミ掲載に限定解除条件はなく、いかなる場合でも掲載不可」 と考えられます。
ただ、禁止されている口コミ掲載は「治療等の内容と効果」に関するものとありますので、 病院の雰囲気やスタッフの応対などは掲載可能とも受け取れます。 たとえば、
「〇〇病院で△△の治療として手術を受けました。結果、長年悩まされていた症状が見事に無くなりま した!」
この口コミは治療内容や効果に触れているため、明らかに掲載NGです。しかし、「〇〇病院の院内はとてもキレイで、明るい雰囲気です。スタッフの方たちの応対も丁寧 で気持ちよく通院できました」
このような口コミでは治療内容や効果には触れておらず、医療広告ガイドラインには抵触 しないと考えられます。
ですが医療広告ガイドラインには「治療等の内容または効果以外の口コミ掲載は可能」と明記してあるわけではありません。
今後も医療広告ガイドラインの内容は常に見直されるでしょうから、慎重に対応しなくてはなりません。
広告とみなされず、口コミ掲載ができるのは?
医療に関する口コミが掲載できるケースは限られています。 まず、医療機関の働きかけがある場合には「誘引性あり」でNGですので、掲載できませ ん。
口コミを掲載できるwebページは、「医療機関から働きかけを受けない、中立的な立場の webページ」です。
たとえばGoogleマイビジネスに登録すると表示されるようになる「Googleレビュー」もそのひとつです。 Googleレビューはその施設の名称を検索したとき、検索結果ページに表示されます。
所在 地や電話番号などの基本情報のほか、口コミも星つきで表示。ユーザーの声がそのまま反 映され、良い口コミも悪い口コミもユーザー次第で増えていきます。
また、患者が自ら口コミを掲載するブログやSNSなどは、医療機関からの働きかけがない 限り「広告」ではありませんので、規制の対象にはなりません。
口コミ掲載に頼らずに集客効果を狙うには?
ホームページは、患者がかかる医療機関を決定するうえでとても重要です。また集客にお いて、口コミは大きな影響力をもちます。
医療機関もその例外ではなく、口コミ掲載をし ているホームページも多くあったのではないでしょうか。
しかし医療広告ガイドラインを 無視するわけにはいきません。 どうすれば患者にとってわかりやすく、誠実かつ訴求力のあるサイトがつくれるのでしょ うか。
「医療広告ガイドライン」ライティングは全研本社にお任せを
今回改定された医療広告ガイドラインの適用で、現在運用しているサイトについて、文章 や内容を変更したり、口コミを削除する必要に迫られているケースも多いでしょう。
しかし、ただ削除しただけでは、サイトを見るユーザーにとってわかりにくく、ニーズを 満たせないサイトになってしまいます。
そこで、全研本社では、医療広告ガイドラインの知識と実践力を備えた専門部隊を用意。 ガイドラインに沿いながらも訴求力のあるサイト制作と運営を任せられます。
全研本社がおこなう医療広告ガイドラインライティングとは?
既にサイトをお持ちの場合、まずは「医療広告ガイドライン」などの規制に抵触するとこ ろがないか、くまなくチェック。抵触箇所の洗い出しをしたら、構成・編集・校閲をしま す。
さらにただ直して終わりではなく、レギュレーションの策定もおこないます。 文言や表現に規定をもたせるため、今後も信頼性の高いサイト運用が可能になります。
新規サイトや新規ページの作成では、医療広告ガイドラインなどの規制に沿ったライティ ングを実施。制限のある表現を避けながらも、口コミ掲載に頼らず訴求力のあるサイトや ページをつくりあげます。
また、サイトのリニューアルにも対応可能。医療広告ガイドラインは今後もアップデートを重ねていくことが予想されますので、それに準じたリニューアルも可能です。
医療機関と患者をつなぐホームページなどのwebサイト。医療広告ガイドラインの知識と実践力をもつ「全研本社」に、安心してお任せください。
この記事を書いた人

- 1,200名以上登録されてるライタープラットフォーム:ライターステーション責任者。2024年より「記事作成代行サービス」や「Hubspot導入支援」、「インタラクティブ動画」など、コンテンツマーケティングに関する支援を開始。
最新の投稿
 コンテンツマーケティング2024-06-14BtoBマーケティングのためのウェビナー活用法
コンテンツマーケティング2024-06-14BtoBマーケティングのためのウェビナー活用法 コンテンツマーケティング2024-06-13コンテンツマーケティングで見込める効果とは?
コンテンツマーケティング2024-06-13コンテンツマーケティングで見込める効果とは? 記事作成2024-06-11記事作成代行サービスを利用するメリットとポイントをご紹介!
記事作成2024-06-11記事作成代行サービスを利用するメリットとポイントをご紹介! 記事作成2024-06-06【2024年版】セールスライティング大全【独自ノウハウも有】
記事作成2024-06-06【2024年版】セールスライティング大全【独自ノウハウも有】