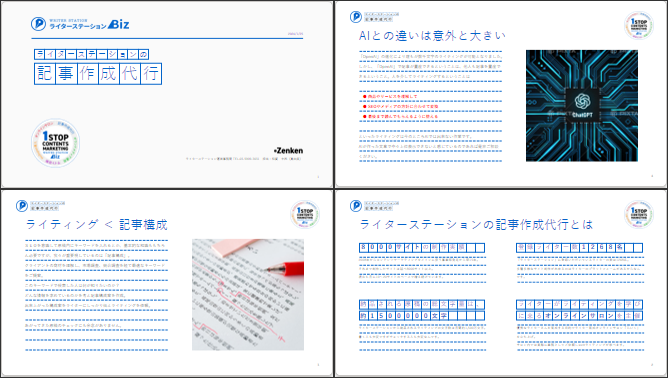WebライティングでやってはいけないNG行動

Webライティングの仕事はすぐにでも始められることもあって、決してハードルが高い訳ではありません。しかし、仕事として成立させていきたいと考えているのであれば、ぜったいにやってはいけないこと、NG行動がいくつもあります。
そこで今回は、webライターがやってはいけないNG行動とはどのようなものがあるのか、なぜそれをやってはいけないのか、解説していこうと思います。
Table of Contents
WebライティングでぜったいNGなこと
Webライティングの仕事を職業や副業として長く続けていきたいのであれば、webライターには知っておかなければいけないNG行動がいくつかあります。
どうしてそれがNGなのか、その理由を含め説明していきます。このNG行動を知らずに原稿を納品してしまうと、クライアント企業に迷惑をかけることになりますので、最低限の知識として確認しておく必要があります。
【コピペ(コピー&ペースト)】
コピー&ペースト、いわゆる「コピペ」は、webライターとして仕事をこなす上で絶対にしてはならないことです。ネット上のメディアや公式サイト、口コミ、SNS、調査データ、論文など、いかなるソースも許可なくコピーして勝手に使うことは禁じられています。
他人の文章や図、画像を無許可で使用してしまうと、著作権を侵害してしまいます。いわゆる「著作物の盗用」にあたります。
仮にコピペが発覚した場合、相手先から損害賠償を請求されるケースもあれば、たった一度のコピペであっても「このライターは他にもコピペをしているのではないか」と疑われることになります。
行為そのものも許されるものではありませんが、ライターとしての信用を損なう行為です。
当然ですが、そのようなライターに仕事を任せようと思うクライアントはいませんので、webライターとして活動したいのであればコピペはぜったいにNGな行動であると認識してください。
コピペには大きく分けて2つのタイプがあります。
ほかのwebメディアなどからのコピペ
ひとつ目は、ほかのサイトのコピペです。これは大げさではなく「犯罪行為」です。
Webライターのみなさんは、ネット上で情報を調べて記事を書いていると思います。なかには個人ブログなども含まれることでしょう。ほかのサイトを参考にすることは問題ありませんが、「これは役に立つ情報だ」とそのままコピペするのは大問題です。
ほかのサイトの文章をそのままコピペした場合、ライターとしての信用度がガタ落ちするだけではなく、作成したサイト自体もGoogleなどの検索エンジンから「コピーしたコンテンツのある価値の低いサイト」だと評価されてしまいます。
最悪の場合、検索エンジンのレギュレーション(規則)で、その公式サイトやwebメディアのページがペナルティを受けて、検索結果に表示されなくなってしまう事態にも陥りかねません。
ライターとして信用を失うだけでなく、依頼主の企業にも大きなダメージを与えてしまうことになるので、コピペがいかに危険な行為かというのがわかると思います。
したがってwebライターのNG行動として、もっともやってはいけない行為のひとつであるといえます。
サイト内記事のコピペや自分がライティングした文章の使い回し
「コピペ」は他人のサイトの文章の盗用が多いのですが、自分が原稿を納品したサイトの文章であっても、コピペとみなされます。これを別の言い方では「重複コンテンツ」といいますが、サイト内に重複コンテンツが多いことによって、検索エンジンの評価もが下がってしまいます。
Webライターが依頼される仕事のなかには、似通った内容の仕事もあります。「前と同じような仕事だな」「他のクライアントから同じような仕事をもらったな」と思うこともあるでしょう。
しかし、そこで「あの時使った文章でいいや」は通用しません。「自分が作った文章」だとしても、納品された原稿の著作権はクライアントに帰属しています。
そもそもだれからコピペをしようとも、既存サイトからのコピペは先にもお伝えした通り検索エンジンからの評価を下げることになります。
また、ユーザー側も「見たことあるな」「手を抜いたサイトだな」と感じるなど、サイトそのものの信頼性を損なうことになります。
根拠のないデータや数字などの情報記載
記事を書くときにいろいろな情報源を参考にすると思いますが、そのサイトがどこから情報を引っ張ってきているか、確認することが大事。とくに数字やデータの場合、根拠となる一次情報や二次情報をリソース(情報源)にして書くのが理想です。
一次情報は自身が集めたデータなど、二次情報は公的機関などが集めた情報のことを指します。ときおり三次情報ともいわれる、「なにを根拠にして書いているのか明記されていないwebメディアや個人ブログを情報源にして書いてしまうwebライターがいますので注意が必要。
数的根拠、データを裏付けるいわゆる「エビデンス」がない情報をもとに文章を書いてしまうと、記事そのものが信憑性に欠ける情報になってしまいます。
「アフィリエイトサイトに書いてあった」では通用しません。公的な研究機関等のエビデンスを情報源として使うようにしてください。常日頃から「この数字はどこかどのような調査をして出てきた数字なのか」という意識を持つことも、webライターのスキル向上に役立ちます。
データや数字などの情報改ざん
根拠、エビデンスの出どころも重要ですが、エビデンスの改ざんは論外です。データやグラフが根拠となっているのだろう…と思いきや、データが改ざんされていることがあります。
よく見ると恣意的に一部を強調していたり、文章を作成するにあたって都合の良い形でデータを取っていたりする場合などは、優良誤認や有利誤認といった、景表法に抵触してしまう事案もあります。
なんとかしてエビデンスを提示してユーザーの興味を引きたいという気持ちはわかりますが、都合のよいデータの抽出・改ざんもまた、ご法度だと覚えておきましょう。
引用の事実と引用元の記載漏れ
引用の場合、「引用であること」を明記しなければなりません。しかし、引用したという記述や説明がない場合、残念ながら「コピペ」「盗用」と判断されてしまいます。
「うっかり引用と明記するのを忘れただけ」だとしても、された側としては「勝手に文章を盗まれた」になりますので、損害賠償請求を受ける可能性もありますし、クライアントからの信頼を損ねることにもなります。
そして引用した事実を記載する際は、引用元の明記も求められます。引用元が記載されていないと、記事を読んでいるユーザーもサイト運営者も、本当に引用元があるのかどうかを確認できないからです。
引用であることや引用元の記載だけでなく、backquoteやciteタグを使って「引用」であることを検索エンジンにも伝えるようにしていきましょう。
引用部分と本文のバランスと主従関係が明確ではない
著作権法第32条で定められている引用の定義には、
- 主従関係が明確であること
- 引用部分が明瞭に区別されていること
- 引用する必然性が認められること
という3つの要素があります。
主従関係
主従関係は、自分の文章が「主」で、引用部分は「従」であるということ。たとえば本文はほんの数行しかないのに、口コミサイトの引用が2,000文字以上もあるというような場合、主従関係が成立していません。本文が1万文字あって、その中に口コミの引用が2,000文字というのであれば、主従関係は成立します。
引用部分の明確化
また、引用文をかぎかっこでくくる、引用タグを使用するといった方法で、本文と引用部分を明確に分ける必要もあります。どこからどこまでが引用なのかがはっきりしていないと、読み手も混乱してしまいます。
引用の必然性
引用する必然性については、引用する文章や図に記事のテーマや内容と関連性が認められるか、引用するに相当する理由があるかどうか、ということが大事になります。
また引用に関しては、句読点も含め、一言一句変更は不可。長い文章の場合は、「前略」「中略」「後略」などと入れて、一部を引用していることを明確に提示してあげる必要もあります。
著作権のある文章の流用
文章の中には著作物として保護されているものもあります。たとえば歌詞がそのひとつです。ブログ程度だから大丈夫だろうと思っても、歌詞の盗用は立派な「著作権の侵害」になります。
相手次第では損害賠償という話にもなりかねませんので、著作権のある文章の流用は気を付けなければなりません。例え歌詞のワンフレーズであっても、文章の長さに関わらず「著作権の侵害」に当たります。
大手クライアントのライティングでは気を付けるとして、個人のブログやアフィリエイトくらいであれば問題ないと思っている方も多いのですが、掲載サイトの規模の大小を問わず、著作物の侵害になるので気を付けましょう。
意識したつもりがなくとも、ついつい同じような文章になってしまうケースもあるだけに、この点は細心の注意が必要です。
ライティングしたものの著作権についても注意が必要
ライティングのお仕事で納品した文章・ファイルは作成したのは自分自身でも、著作権はクライアントに帰属します。つまり、「自分のもの」ではありません。
当然ですが他のクライアントに同じファイルを提出するなど言語道断ですし、「自分が作成しました」と告げることさえ禁止のケースもあります。納品した後は、自分の手を離れていることも覚えておきましょう。
画像を無許可で加工して使う
画像や図を引用元を明記したうえで引用することがあると思いますが、その際画像や図に加工をするのはNGです。ものによっては、無許可での引用や転載が禁止されているものもあります。
たとえば他のサイトの画像を引用する場合、「もう少し格好良くしよう」と背景などに手を加えたり、あるいは画像を反転させたりするなど、どのような些細な加工もやってはいけないNG行動です。
プロのwebライターとしてNGなこと
一度引き受けた仕事を途中でやめてしまう
一度引き受けた仕事は最後までしっかりと引き受けることが鉄則です。引き受けてから「無理かも」「自分に合わない」と思い、「やっぱり辞めます」と思いたくなることもあるかもしれません。
しかし、打診された時点で「これは向いていません」と断るのであれば問題ありませんが、一度引き受けた仕事を「やっぱり無理です」と断るのはWwbライター云々ではなく、社会人としてNGです。
たとえきちんと事前に連絡を入れたとしても、いったん受けた仕事は最後までやり通すことがプロとして最低限のマナーです。
特に、顔が見えない分、無責任に逃亡する人もいるのですが、その瞬間、二度と同じクライアントからのお仕事を引き受けることはできないことを覚悟しておきましょう。
連絡もせずに飛んでしまう
こちらは社会人としてというよりは、人としてやってはいけないNG行動です。依頼主は必要に迫られてwebライターにライティングを依頼しているわけです。
もしその原稿が納品されないとなれば、ほかのwebライターを探したり、急遽社内で対応せざるを得なくなったりするわけです。これは非常に迷惑な話です。
連絡もせずに飛んだwebライターは、二度とその会社では仕事ができないだけでなく、めぐりめぐって自分の評価もどん底まで下げることになります。
「自分はまだプロじゃないから、しらばっくれても大丈夫だろう」などと甘い考えをもっている人がいたら、プロのwebライターになるのはあきらめるしかありません。
納期を守らず何度も締め切りを破る
納期は一度決まったら厳守です。もちろん納期を決める前であれば「もう少し期日が欲しい」といった要望を伝えることはありですが、一度双方が納得して決められた納期は、必ず守るべきです。
仕事を依頼したクライアントとしても、納期に合わせてどうするかを考えていますので、納期がずれることでクライアントに大きな迷惑をかけることになります。
その結果当然のことですが、ライターとして、さらにはいち社会人としての信用を損なうことになります。締め切りを守らないwebライターに寛容な企業のほうが、圧倒的に少ないと思ってください。
たとえクライアントの担当者から連絡が滞るようなことがあっても、自分自身は即レスを心がけ、納期をしっかりと守るようにしましょう。
指定文字量よりも少ない、指定文字数を守らない
基本的に、webライティングの仕事はクライアントから「何文字で書いてください」と文字数が指定されています。そして、その文字数に大きな理由はないと思うかもしれませんが、クライアントはいろいろ考えたうえで、その文字数を決めています。
「予定の文字数に足りませんでした、すみません」は通用しません。だからといって同じ文章の言い回しを連続するなど無駄に文字数を稼ぐのもご法度です。
また、「1,000文字程度」「1,000文字前後」「およそ1,000文字」など、表現にバラつきがあるとなにが正解かわからないので、そのような場合は自分で勝手に判断するのではなく、クライアントに文字数について確認するようにしましょう。
さらに指定された文字数よりも大幅にオーバーした文字数で書くのもやめましょう。多少は増えても問題ない場合が多いですが、webメディアのコラムなど文字数が多いとスペースに収まらないといった問題が起こる可能性もあるので、できるだけ指定された文字数+100文字程度をマックスと考えるとよいと思います。
「~だと思います」「~だそうです」などあいまいな文末
慣れていないと、どうしても文末が「~だと思います」「とのこと」「だそうです」といった、あいまいな文末に終始してしまいます。ブログであれば問題ありませんが、プロのwebライターが書いた文章としてはあまり感心しません。
すべてが推測で終わるのではなく、一部だけであるなら問題ありませんが、確かな情報源をもとに事実を盛り込んでいる文章を書くのであれば、言い切ってしまうほうが読者からの信頼も得られるというもの。
プロであると自負したいのであれば、文章の文末にまでこだわって書いていくようにしてください。
ネガティブ表現を何度も使う
ときにはどうしてもネガティブな表現が出てしまうこともあるものですが、ネガティブな表現もまた、あまり好ましいものではありません。そもそも、クライアントがネガティブな表現を望まないはずです。
不満や不安をあおって興味を引く「炎上ビジネス」もあるにはありますが、企業名が表に出るような仕事では、ネガティブ連発をよしとする仕事はあまりないはずです。
もしネガティブな要因があるのであれば、「成分を見ると利用者の負担が懸念されます」といったように、あくまでも「客観的な事実」のみを盛り込むようにしてください。
NG行動をしないwebライターを目指すなら
ここまでwebライターがやってはいけないNG行動について説明してきましたが、知らないうちにやってしまっていたことが、いくつあったでしょうか?おそらくひとつもない、というwebライターのほうが少ないのではないかと思います。
今回はNG行動について解説しましたが、何度もクライアントからwebライティングを依頼されるライターになりたいのであれば、以下のことをちょっと意識してみてください。
ユーザーもクライアントも、どちらも満足してくれる文章が書けるwebライターとして成長していけるはずです。
相手がベネフィットを感じる文章にする
ときにご自身の文章に酔うというか、「いい文章だから評価されるだろう」という意識が強くなってしまうことがあります。しかし自己満足で文章を書いても、あまりいい結果は望めません。
読者に文章を読んでもらいたいのであれば、読者がベネフィット(利益、恩恵)を感じる文章を書くように心がけてください。
たとえばお店を紹介する記事を書く際、ただ「良いお店です」「満足できるお店です」と書いてあるだけでは、読者としてはなにが良いのか、どう満足できるのか、よくわかりません。
しかし、「バリアフリーなので車いすの方でも安心」「クレジットカードが使えるので現金がなくとも安心」といったように、具体的な情報があれば、それらの情報を求めている人に「ベネフィット」を与えることができます。
クライアントではなく読者(ユーザー)のほうを向いて書く
基本的に文章作成はクライアントを通して、その先にいる「読者」のために書くものです。自分の満足やクライアントに気に入られる文章ではなく、あくまでも「読者に有益」となる文章を届けていくべきです。
読者にとって有益な情報であれば、すなわちクライアントとっても有用なコンテンツであるということです。クライアントの要望に応えることも大切ですが、大前提として「読者のために書く」という気持ちを忘れることなく、研鑽を積んでいってください。
この記事を書いた人

- 1,200名以上登録されてるライタープラットフォーム:ライターステーション責任者。2024年より「記事作成代行サービス」や「Hubspot導入支援」、「インタラクティブ動画」など、コンテンツマーケティングに関する支援を開始。
最新の投稿
 コンテンツマーケティング2024-06-14BtoBマーケティングのためのウェビナー活用法
コンテンツマーケティング2024-06-14BtoBマーケティングのためのウェビナー活用法 コンテンツマーケティング2024-06-13コンテンツマーケティングで見込める効果とは?
コンテンツマーケティング2024-06-13コンテンツマーケティングで見込める効果とは? 記事作成2024-06-11記事作成代行サービスを利用するメリットとポイントをご紹介!
記事作成2024-06-11記事作成代行サービスを利用するメリットとポイントをご紹介! 記事作成2024-06-06【2024年版】セールスライティング大全【独自ノウハウも有】
記事作成2024-06-06【2024年版】セールスライティング大全【独自ノウハウも有】